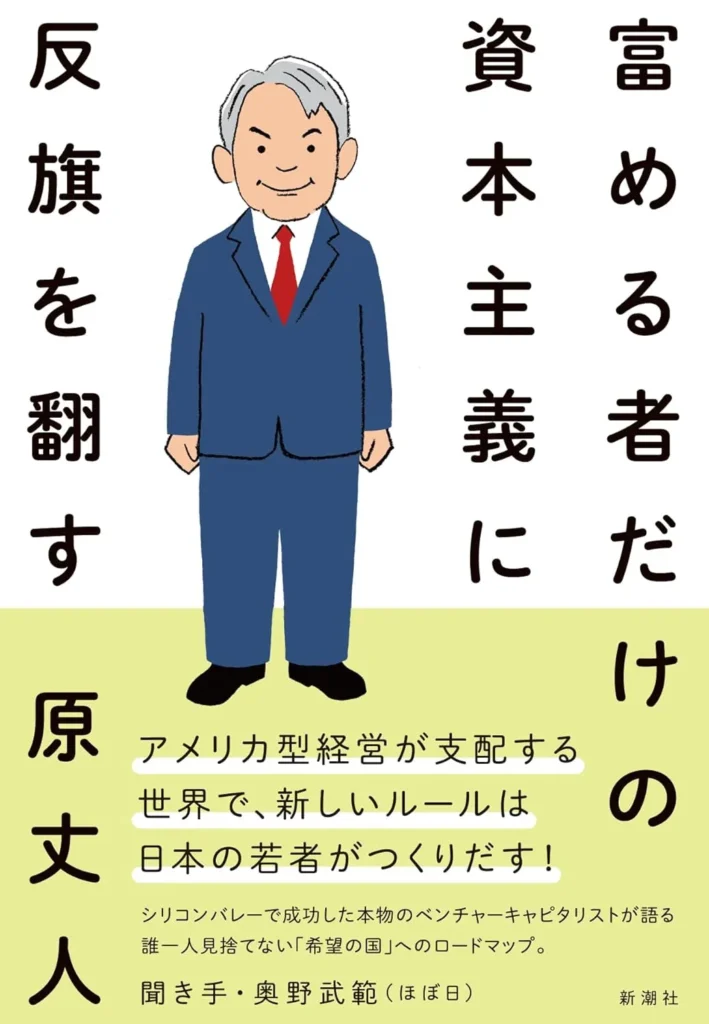※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
富める者だけの資本主義に反旗を翻す
原丈人
在学中にシリコンバレーで光ファイバーディスプレイ開発メーカーを創業。デフタ・パートナーズを創業し、情報通信、半導体技術、創薬等のベンチャー企業に出資、経営を行う。
新潮社
- はじめに
- 第1章 大切なのは「自分の頭で考える」こと。 他人の決めたルールがおかしいと思ったら、どうする?
- 父は、あこがれ。信念の人
- 鉄道模型の知識や技術をコクヨで活用
- 技術の力で、多くの人を幸せにする
- 競合他社をつぶすなと言い続けた祖父
- 母から教わった 「公平であること」の重要性
- ひとりだけ長髪を貫いた中学時代
- 校則を破るなら「きちんとした身なりで」
- 病院のベッドでドイツ語を習得した高校時代
- 自分の頭で考えなければ、新しいものは生まれない
- 各国の政府顧問を引き受けてきた理由
- 公益資本主義とは何か
- 世界があこがれる日本をつくりたい
- 第2章 自分の目で見よう、肌で感じよう。 机の上の勉強だけじゃわからないことだらけ!
- 大学入学祝いは、共産圏への旅費!!
- ポーランドで見た共産主義の矛盾
- 中央アメリカで「考古学」と出会う
- 第3章 解決策は、必ずどこかにある。 困ったときこそ「自分の頭で考える」が試される
- エルサルバドルで人生の師と出会う
- 大学卒業後、本格的に考古学の道へ
- なぜか海外ツアーを主催することに
- 「自分も将来、こういう仕事がしたい」
- 最後に待っていた、大ピンチ!
- 第4章 なぜ学ぶ? 人生を切り拓くために。 大学とは夢を実現するための武器を得るところ
- 考古学の資金を稼ぐためにスタンフォードへ
- ビジネススクールから工学部へ
- ノーベル賞受賞者に生化学を学ぶ
- 伝説の起業家たちとの「ブラウンバッグランチ」
- 第5章 人は「信頼」されると 「奮起」します。 リーダーになったら、まずは仲間に信頼を与えよう
- 光ファイバーディスプレイの会社をシリコンバレーに設立
- はじめて注文してくれたのは「ディズニー」だった
- ディズニーが教えてくれた 「信頼」の大切さ
- 東京ディズニーランドの技術顧問に
- 第6章 大好きなものがあることの、つよさ。 「好き」こそが将来の可能性を広げてくれる
- ジョブズの Apple を急成長させたもの
- ベンチャーキャピタルの道へ
- 出資金は「ちょっと足りないくらい」がいい
- はじめての出資はウォロンゴング社
- 国防総省の役人をリクルートする
- 出資の基準は「考古学に役立つかどうか」
- なぜ、テクノロジーが重要なのか
- 第7章 夢のまた夢? それ、実現できるかもよ? イメージは「見えない階段を1段ずつ」登ること
- バングラデシュの遠隔教育・遠隔医療
- アフリカの栄養不良を解決するために
- 見えない階段を1段ずつ登っていく
- 第8章 ルールやシステムは、もっとよくできる。 いい子で従ってるだけじゃ何も変わらない
- 格差社会の原因となる株主資本主義
- なぜ短期主義がいけないのか
- 大銀行家との議論
- まじめに働く人が報われる社会に
- ルールの変更で日本人の給料を上げる
- 株価に一喜一憂する必要はない
- 公共投資も公益資本主義の発想で
- 香港をハブに日本と中国を結ぶ
- なぜいま香港なのか
- 公益資本主義を浸透させるために
- 第9章 尊敬する人を見つけよう。 その人から学ぼう、その人の話を聞こう
- 自分の頭で考えて、自分で決めること
- 現地へ行くこと
- 長い時間軸で考えること
- 失敗の経験から学ぶこと
- 最後は「人」
- わたしが影響を受けた人物
- 従業員とその家族を守るのが企業の使命
- 日本を「希望の国」にする
- おわりに
書籍紹介
本書の核心は、資本主義が本来持つべき「機会の平等」を取り戻すための提言にあります。原氏は、現在の経済システムが一部の富裕層にのみ利益をもたらし、多くの人々を置き去りにしていると指摘します。特に、技術革新やグローバル化が加速する中で、労働者の賃金が停滞し、中間層が縮小している現実を、統計や事例を通じて明らかにしています。しかし、この問題を単に批判するだけでなく、解決策として、ベンチャー投資や教育改革、さらには地域コミュニティの強化といった具体的なアプローチを提案しています。これらのアイデアは、著者自身の経験に裏打ちされており、机上の空論ではなく現実味を帯びたものとして読者に響きます。
本書の魅力は、難しい経済問題を身近な視点で語る平易な文体にもあります。専門的な知識がなくても、資本主義の仕組みやその課題が理解できるように、例え話や実際のエピソードが効果的に織り交ぜられています。例えば、シリコンバレーの成功物語の裏に隠された格差の実態や、日本の地方企業が直面する資金調達の壁など、具体的なケースを通じて問題の本質を浮き彫りにしています。このような語り口は、経済や社会問題に関心がある幅広い読者にとって、親しみやすく、考えを深めるきっかけとなるでしょう。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
株価に一憂する必要はない

株主と社員の給料の分配を、少し社員の給料に偏らせれるルール変更がなされたとしましょう。日本人の株保有者の1割が損をすることになりますが、9割の国民には関係ありません。
社員への待遇には関係なく、株を買う人の評価によって株価が上下します。その株価を表示する電光掲示板が首相執務室や財務大臣の部屋に備え付けられています。株価も重要な政治材料とされていることでしょう。
懸念していることは、株式を保有する国民が全体の1割であり、20代などの若い世代では「4%」と若い世代ほど株を保有していません。