※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
正しくニュースを理解するために
今さら聞けない
日本政治の超基本
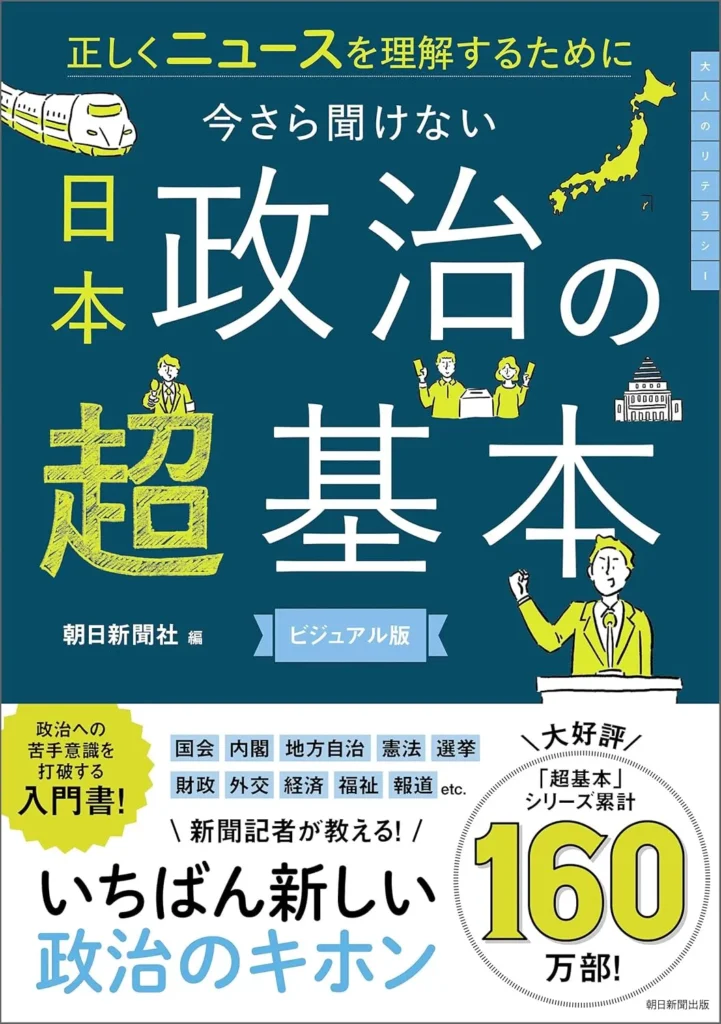
朝日新聞社
- 日本の歩み 政治の主体はこう変わってきた
- 俯瞰で見る 私たちの日常と政治
- 年間の 主な政治スケジュール
- どれだけ知っている? 私たちと政治 CheckList
- Chapter1 政治と選挙
- 日本の選挙制度
- 選挙は何のためにあるの?
- 現在の選挙方式
- 「選挙区制」と「比例代表制」の違い
- 国政選挙の種類
- 衆議院と参議院の選挙は違うの?
- 衆議院議員選挙
- 衆議院選挙では3つの投票を行う
- 参議院議員選拳
- 参議院は解散がなく3年ごとに半分を選ぶ
- 投票の方法
- いつ・どこで・どうやって投票するの?
- 開票の方法
- 開票はどうやって行われるの?
- 選挙運動のルール
- 選挙に立候補するにはどうすればいい?
- 選挙の問題点
- 若い世代の投票率はなぜ低い?
- 一票の重みは選挙区によって違う
- Column 「自治体選挙の投票率が落ち込んでいる」
- 日本の選挙制度
- Chapter2 政治思想と政党
- 政治的立場
- 右翼と左翼は何が違うの?
- 政党
- 政党は政策実現のために集まったグループ
- 日本の政党の政治思想
- 政党によって考え方や立場が違う
- 与党と野党
- 政権を運営する政党とそれ以外の政党
- 政権交代とはどういうこと?
- 政治活動をするためのお金
- 政治資金はどうやって集めているの?
- 日本の主な政党
- 自由民主党ってどんな政党?
- 自民党を代表する政治家 田中角栄
- 自民党を代表する政治家 中曽根康弘
- 自民党を代表する政治家 小泉純一郎
- 自民党を代表する政治家 安倍晋三
- 公明党ってどんな政党?
- 立憲民主党ってどんな政党?
- 日本維新の会ってどんな政党?
- 国民民主党ってどんな政党?
- 日本共産党ってどんな政党?
- そのほかにはどんな政党があるの?
- 自由民主党ってどんな政党?
- Column「各国の統治体制にはさまざまな形がある」
- 政治的立場
- Chapter3 政治の仕組み
- 政治の役割と三権分立
- そもそも「三権分立」って何?
- 国会
- 国会では何が行われているの?
- 国会の仕組みを知ろう
- 衆議院と参議院、2つあるのはなぜ?
- 法律はどうやって作られるの?
- 国会議員はどんなことをしているの?
- 委員会では何が行われているの?
- 審査会は何をしている?
- [国会ってどんなところ?]
- 内閣
- 内閣では何が行われているの?
- 内閣の仕組みを知ろう
- 予算案はどうやって決めているの? 総理大臣は何をする人?
- 組閣とは総理大臣のチーム作り
- 内閣改造は何のために行う?
- 総理大臣を選び直す内閣総辞職とは
- 「行政主体」「行政機関」と1府省庁とは
- 1府13省庁にはどんな役割があるの?
- 各種行政機関「庁」の役割とは
- 各種行政機関「委員会」の役割とは
- 官房長官は何をする人?
- 諮問機関って何をしているの?
- [首相官邸ってどんなところ?]
- 司法
- 裁判所の仕組みを知ろう
- 憲法の番人としての最高裁判所の役割
- 裁判の種類と裁判員制度とは?
- 違憲審査権は憲法違反を判断する権限
- 地方自治
- 地域の人々のための地域の人々による政治
- 地方自治と国の政治は何が違うの?
- 条例、直接請求、住民投票とは?
- Column 「死刑制度、先進国で維持しているのは少数」
- 政治の役割と三権分立
- Chapter4 政治と憲法
- 日本国憲法の誕生
- そもそも憲法はどうやってできた?
- 憲法の役割
- 権力の乱用を防ぎ、国民の権利を守る
- [憲法前文には何が書いてあるの?]
- 日本国憲法の三大原則
- 国民主権ってどういうこと?
- 基本的人権の尊重ってどういうこと?
- 平和主義ってどういうこと?
- 改正の手順
- 憲法を改正するにはどうする?
- Column 「権威主義の台頭で揺らぐ民主主義」
- 日本国憲法の誕生
- Chapter5 近年の主な政治課題
- 国家財政
- 政府のお金の収入と支出の仕組み
- 税金の種類を知っておこう
- 社会保障費が増えている
- 「103万円の壁」とはどういうこと?
- 無駄遣いをしている公共事業はない?
- 世界の中の日本
- 日本の経済規模はどのくらい?
- 外交
- G7 G20 とは何か?
- 戦争・紛争当事国との関わりは?
- 日本とアメリカの関係はどうなっている?
- 日本と深い関係にある中国
- 戦後の日本と韓国との関係
- 戦後ロシアの歴史と日本との関わり
- EU、ASEAN、アフリカ諸国との関係
- 防衛
- 自衛隊の歴史とその役割とは
- 日本の安全が脅かされる中での防衛政策は?
- 農林水産
- 日本の農業、漁業は大丈夫?
- エネルギー・環境
- パリ協定を受けた「2050年目標」達成への取り組み
- 経済
- 「物価高」インフレ・デフレに対応する政策
- 日本銀行の役割とは
- 少子高蛤化
- 日本の高齢化は世界トップクラス
- 増え続ける高齢世代を支えきれなくなる
- 東京一極集中
- 東京一極集中が止まらないのはなぜ?
- 働き方改革
- 働き方改革が人手不足ニッポンを変える?
- 多様性社会
- 「ジェンダー問題」は世界から遅れている
- 経済格差
- 25「相対的貧困率」から見える日本の経済格差
- Column 「遅れた女性の政治参加、諸外国に学ぼう」
- 国家財政
- Chapter6 メディアと政治と市民の関係
- メディア
- 政治に対する報道のあり方とは
- 記者クラブとは
- 各種団体
- 政治と団体の関係
- 政党と深い関わりを持つ経団連と連合
- 政治参加
- 政治に参加する方法はいろいろ
- Column 「SNSと政治参加」
- メディア
- 付録
- おさえておきたいトピック
- ニュースによく出てくる政治用語
- 歴代内閣総理大臣と主な出来事
書籍紹介
政治に苦手意識を持つ方でも気軽に手に取れる入門書として、超基本シリーズの15作目にあたります。
本書は、日本の政治の仕組みをわかりやすく解説することを目的としています。選挙のルールや政党の役割、国会運営の仕組み、内閣の機能、さらには地方自治のあり方まで、普段ニュースで耳にするキーワードを丁寧に紐解きます。特に、選挙で適切な候補者を選ぶための知識や、正しい政治が行われているかを判断するための視点を提供してくれる点が魅力です。最新のデータを基に、新聞記者がわかりやすく説明しているため、専門的な知識がなくても読み進められます。
選挙制度の仕組みや国会の議席分布など、複雑なトピックも図表を通じて直感的に把握できます。1章では選挙と政治の基本を、2章では政治思想や日本の立ち位置をテーマに、ニュースを正しく読み解くための土台を築いてくれます。選挙一つをとっても、投票の仕組みやその問題点を知ることで、自分が政治に参加する意義を再認識できます。また、国際的な視点から日本の政治を捉えるパートもあり、グローバルな文脈での日本の役割を理解する手助けとなります。政治が遠い存在ではなく、日常生活と密接につながっていることを実感できるでしょう。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
日本の政党
②公明党ってどうんな政党?
公明党は、創価学会から政治部門にわかれて1964年に結成した政党です。99年に自民党と連立政権を発足させています。
⑤国民民主党ってどんな政党?
2012年に下野した旧民主党勢力が立件民主党と国民民主党に分裂しました。
国民民主党は「穏健保守からリベラルまでを包摂する改革中道政党」と掲げ、政策実現のために自民党政権に協力することもあります。2023年度政府予算案にはガソリン税引き下げのためとして野党として異例の賛成をしています。
2024年衆院選では、選挙区で立憲との候補者1本化」や政策協議は難航していますが、現役世代をターゲットにした「手取りを増やす」政策を掲げ、議席数を増やしています。
- 2024年の政策
- 給料・年金が上がる経済の実現
- 消費と投資を拡大、持続的な賃上げの実現
- 年金アップの実現
- 自分の国は自分で守る
- 災害対応を強化
- 総合安全保障に万全を期す
- 主権を守り抜く
- 人づくりこそ、国づくり
- ヒトへの投資
- 若者減税就職氷河期対策
- 働き方改革・医療改革
- 正直な政治をつならぬく
- 給料・年金が上がる経済の実現
国民民主党は課税最低ラインを年収103万円から178万円に引き上げるように主張し、2025年度政府予算案に反対しています。
国の借金は増えてもいい?
米国の経済学者らがMMT(Modern Monetary Theory)という学説を提唱し、自国通貨を持つ国は借金をしてもその分だけ通貨を刷ればいいので破産などしないという論理が広まりました。
しかし、企業と国民が潤って税収も増えると期待されていたMMTですが、貧富の差の縮める効果はなかったようです。実際、通貨の価値が下がるインフレを引き起こし、経済的に弱い人にしわ寄せがいく副作用があります。
国債を発行し過ぎると、低所得者層の賃金の上昇が物価の上昇に追いつかず、実質賃金が下がってしまうというリスクです。
相対貧困率
国や地域の中で経済格差を測る指標の1つが相対貧困率です。
所得が集団の中央値の半分にあたる「貧困線」を下回る人の割合を指します。手取り収入が中央値以下の人の分布です。「G7の中では日本が一番貧困率が高い」といった証明によく使われます。
この相対貧困率が高くなることが、防寒着も買えないといった最貧困層を可視化するものとして使われています。子どもの9人に1人が貧困だという社会問題を取り上げるときに貧困率の推移などが利用されているようです。
2023年に発足されたこども家庭庁は、この子どもの貧困問題を取り上げ、少子化対策とともに、子どもの様々な課題解決を目的としています。

