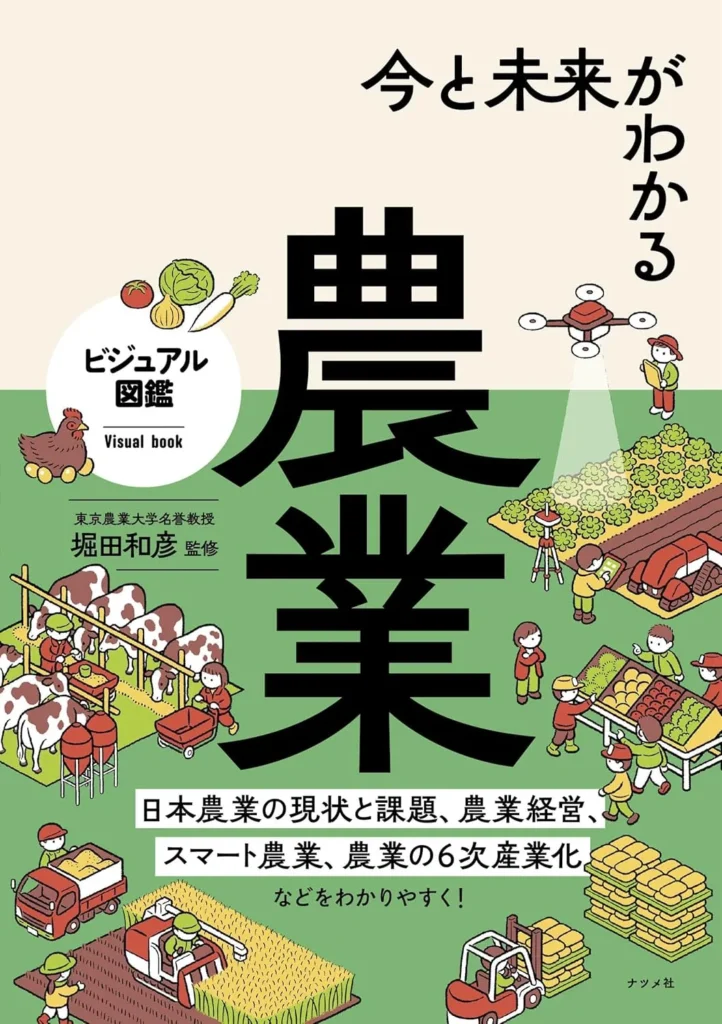※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
今と未来がわかる農業
堀田和彦
食農連携コーディネーター。
東京農業大学名誉教授。
農商工連携による地域活性化の方法。
ナツメ社
- はじめに
- 第1章 日本の農業の現状と課題
- 日本の農地は国土のわずか11%
- 需要減で変化を迫られる生鮮品生産中心の構造
- 農地の半分を占める水田、 面積、生産額とも減少傾向
- 農家の大半は家族経営、 進む就業者減と高齢化
- 農地の利用状況に見る農業の衰退
- 地域の農業を維持する集落営農の現状
- 長年続いた減反政策とコメをめぐる状況
- おもな食料の自給率は低下する一方
- 国際情勢の緊張で注目される食の安全保障
- 増加する肉の消費、農業産出額で畜産は最多
- 国産花きを圧迫する輸入花きの増加
- 低下する生鮮食品の卸売市場経由率
- 需給調整が難しい生乳、9割は指定団体経由で流通
- 対応が急がれる農産物の物流危機
- 肥料の原料は輸入依存、求められる安定調達
- コメの現物市場と先物取引がスタート
- 就農へのステップ1 夢見るだけでなく現実を見つめる
- 第2章 新たな農業経営と就農の潮流
- 規模の拡大が進む日本の農業経営体
- 減少する新規就農者、内訳に見る大きな変化
- 女性の就農を支援する家族経営協定
- 企業による農業参入の急増と立ちはだかる壁
- 農業法人の種類とメリット、デメリット
- 農業法人への就職と雇用形態
- 生産性向上のために進められる農地集積
- 注目されるフランチャイズ型の農業
- 存在感を高める農のスタートアップ
- 広がる就農相談、就農準備サービス
- 新規就農者を対象にした研修プログラム
- 農業経営者を養成する教育機関と育成研修
- 新規就農にかかる費用と自己資金、支援制度
- 都市農業の現状と生産緑地の意義
- 就農へのステップ2 農業の厳しい面を知っておく
- 第3章 農産物をめぐる内外の動向
- 減り続けるコメの需要と現状に応じた取り組み
- 高収量化と生産費減でコメの競争力を向上
- ブランド米の人気と市場のニーズ
- 輸入頼みの小麦、 国産化への取り組み
- 自給率6%の大豆、 困難な事情と課題
- 穀物高騰にあえぐ畜産業、 国産飼料増への取り組み
- 施設栽培の比重と期待が高まる野菜
- 指定野菜の価格を安定させる制度
- 高品質化、大規模化で競争力を高めた国産牛肉
- 10万羽以上の生産者が採卵鶏の約8割を飼養
- 工場生産、企業化により様変わりするきのこ類
- 果物は高評価が定着、 産出額、 輸出額が増加
- 農林水産物・食品の輸出拡大への取り組み
- 海外で人気の日本産牛肉、ライバルの「Wagyu」
- 減少する緑茶の消費と抹茶の世界的ブーム
- グルテンフリーが広まり注目される米粉
- 世界の種苗市場の寡占化と遺伝子操作
- 感想へのステップ3 情報を収集し、家族の理解を得る
- 第4章 持続可能な成長をもたらす農業とは
- 世界の土壌の3分の1が劣化している現状
- 海洋流出が問題となる肥料のプラスチック被覆材
- 環境負荷の低い無洗米が循環型農業にも貢献
- 気候変動が農業に及ぼす甚大な影響と対策
- 気温の上昇がもたらすワイン生産現場の変化
- 持続可能な農業を目指し日本が進む道程
- 伝統ある農業システムを世界農業遺産に認定
- 中長期の目標、 みどりの食料システム戦略
- 持続的な改善活動である農業生産工程管理GAP
- 重要性の増す有機農業と有機農産物
- 化学農薬のみに頼らない総合防除(IPM)
- 国外から侵入する病害虫への対策
- 植物工場による高効率の安定供給
- 畜産環境問題における家畜排せつ物の利活用・
- トレーサビリティとHACCPの制度
- 環境への負荷を示すフードマイレージ
- 畜産業界で求められるアニマルウェルフェア
- 就農へのステップ4 専門家に相談しながら計画をかためる
- 第5章 スマート農業は未来を拓くカギとなるか
- 広がるスマート農業とその可能性
- 自動走行し、作業を行うトラクターなどの農機
- 衛星、 ドローンによるリモートセンシング
- データを有効活用する経営・生産管理システム
- 重労働の負担を軽減するアシストスーツ
- 省力化にとどまらず期待される搾乳ロボット
- 施設園芸における環境制御と生産性の向上
- 鳥獣被害対策におけるスマート技術の活用
- トラクターと作業機の通信規格ISOBUS
- 広がるスマート農業技術活用サービス
- 農業データを連携させる基盤WAGRI
- 就農へのステップ 5 移住前から現地に通い準備を進める
- 第6章 各方面から進む6次産業化の動き
- 農業・農村を再生する6次産業化の取り組み
- 6次産業化を阻む壁と成功へのヒント
- 雇用・所得を創出する農山漁村発イノベーション
- 大規模水田経営において多角化が必須である理由
- 生産者と消費者が連携、 地域支援型農業
- 農山漁村での起業を促進する INACOME
- 有名企業の農業参入と広がる取り組み
- 農村ツーリズムによる収益確保と雇用の創出
- 農産物の料理提供、 収穫体験による誘客
- 6次産業化の中核、 農産物直売所
- 地域の特産品を保護、活性化につなぐ制度
- 障害者福祉と農業の農福連携の動き
書籍紹介
本書では、まず日本の農業が置かれている現状に焦点を当てています。高齢化が進む農業界では、従事者の平均年齢が70歳近くに達し、後継者不足が深刻な問題となっています。さらに、耕作放棄地の増加や食料自給率の低下、気候変動の影響など、さまざまな課題が浮き彫りにされています。これらの問題をデータに基づいて詳細に分析し、読者にわかりやすく提示している点が本書の強みです。農業に詳しくない方でも、現在の農業界がどのような状況にあるのかを把握しやすい内容になっています。
農業の未来に対する希望や可能性についても深く掘り下げています。たとえば、農家の大規模化や植物工場による安定した生産、スマート農業やドローンの活用といった技術革新が紹介されています。これらの新しい試みや成功事例を通じて、日本の農業が再び活力を取り戻す可能性を示唆しています。特に、スマート農業がどのように未来を切り開く鍵となるのか、その具体的な事例や展望が丁寧に描かれています。
日本の農業の現状と課題から始まり、新たな農業経営の潮流や農産物の内外動向、持続可能な成長をもたらす農業のあり方、そしてスマート農業の可能性へと展開していきます。これらのテーマを通じて、読者は農業が単なる生産活動ではなく、社会や経済、環境と深く結びついた分野であることを実感できます。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
クボタのアグリロボシリーズ

現在、メーカー各社が開発にしのぎを削っているのが、無人自立走行の農業機械です。現場にいる必要がないため、非常時に遠隔操作をするくらいの作業しかありません。AI技術で周囲の状況を判断し、耕耘、収穫などの作業を行える農機の開発が盛んです。
2017年からアグリロボシリーズを発売し、トラクター、田植え機を展開してきました。2024年に発売された無人自動運転のコンバインは、人が田畑を一周しながら米や麦を刈り取ると、以降は無人で刈り取りができるという機械です。誤差は、なんと2~3センチで障害物があった場合の安全装置も完備しています。