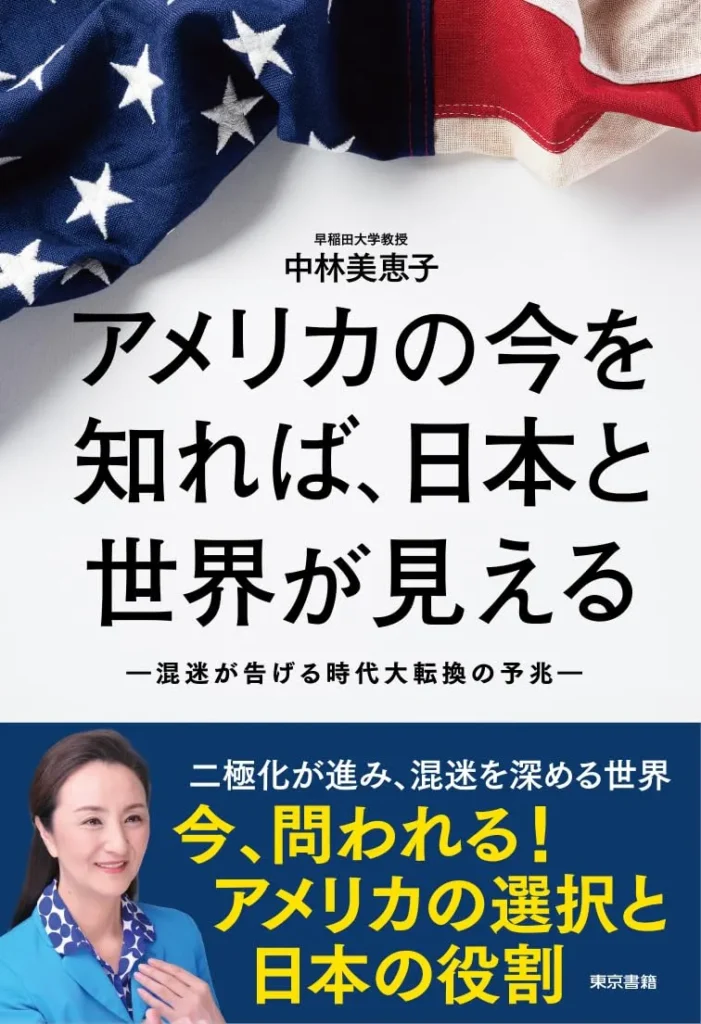※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
アメリカの今を知れば、日本と世界が見える
混迷が告げる時代大転換の予兆
中林美恵子
早稲田大学教授。1992年に米国永住権を核都市。同年、米国家公務員として連邦議会上院予算員会に正規採用され、上院予算員会の共和党側に勤務。約10年間、米国の財政・政治の中枢で予算編成の実務を担う。
東京書籍
- はじめに
- 序章 戦争とインフレがアメリカの分断を加速
- ウクライナ戦争・パレスチナ問題
- ウクライナ戦争とアメリカ世論
- ウクライナ戦争の戦況で変化するアメリカ世論
- アメリカが軍事行動を起こすとしたら?
- アメリカの対ウクライナ支援
- 冷める世論
- ウクライナ支援とトランプ前大統領の再登場
- イスラエルの対ハマス攻撃
- 民主党・共和党それぞれの対応
- 高進するインフレ
- もう1つの課題「経済」
- ガソリン価格高騰が貧困層を直撃
- バイデン大統領の中東訪問
- トランプ前大統領再登場の理由はバイデン政権の経済政策の失敗
- ウクライナ戦争・パレスチナ問題
- 第1章 アメリカ合衆国という国の成り立ち
- アメリカ合衆国憲法の制定
- トランプ前大統領、狙撃される
- 合衆国憲法修正第2条と銃規制
- アメリカ独立と「大陸会議」
- 「主権ある州」と「連合規約」の成立
- 「やくざなヤンキー」、「しらみだらけの田舎もの」
- 妥協の産物としての「連合規約」の限界
- 「アナポリス会議」での「大会議」の提案
- 「大 会議」開催への険しい道のり
- 「大会議」は秘密裏に進められた
- 「バージニアプラン」から「合衆国憲法」
- 「合衆国憲法」
- 連邦制を明記
- 「三権分立」
- 憲法批准とアメリカ合衆国の成立
- 憲法を修正する
- 権利章典
- 基本的人権の保護・人民が武器を保有し、携帯する権利
- アメリカ独立記念日頃に集中する銃乱射事件
- きわめてアメリカらしい基本的理念
- その後の憲法修正
- 南北戦争と奴隷制廃止
- 奴隷制禁止とセットの平等条項
- 禁酒修正条項と禁酒修正条項の廃止
- 女性の参政権
- 戦後日本でも女性が参政権獲得
- アメリカの州と合衆国
- ドル紙幣とアメリカ
- 1ドル紙幣の表面……発券銀行
- ードル紙幣の裏面 「IN GOD WE TRUST」
- 1ドル紙幣の裏面・・・・・国璽
- アメリカは西に向けて広がった
- 連合国家と政府間関係
- 州は国家のような存在
- 公選職員で運営される郡(カウンティ)
- 警察や検察組織を持つ自治体
- 州が課税権を持つ
- 州間で企業誘致競争
- 課税や福祉面での州間競争
- 州の競争が起きている
- アメリカ合衆国憲法の制定
- 第2章 アメリカの司法と政治
- アメリカの裁判所制度
- 連邦制と三権分立のアメリカ
- 三権分立と「抑制と均衡」
- 連邦裁判所と大統領の関係
- 日米の裁判制度の違い
- 州裁判所はきわめて身近な存在
- アメリカの州裁判制度
- 地方裁判所と政治
- メリーランド州の裁判制度
- 連邦裁判所(最高裁・控訴裁・地方裁)
- 連邦裁判所 の裁判官は大統領による任命
- 連邦最高裁判所による違憲審査
- 裁判と政治
- 司法の場は政治運動の第一歩
- ブラウン対トピカ教育委員会裁判
- ブラウン判決から公民権運動へ
- 三権分立の司法と政治
- (1)銃規制と憲法修正第2条
- (2)人工妊娠中絶をめぐる判断
- (3)地球温暖化とEPA規制
- 保守的な最高裁判事を任命
- 連邦最高裁判所への信頼度は低下傾向
- アメリカの裁判所制度
- 第3章 連邦議会と二大政党・
- 連邦議会の制度
- 停止した政府機能
- アメリカ国旗に象徴される連邦制
- 連邦議会は上院・下院の二院制
- 異なる選出基盤からの選出で権力分散を図る制度
- アメリカでは行政と立法が完全に独立している
- 合衆国憲法の「一丁目一番地」は連邦議会
- 日本の国会での立法過程・①法律案作成・②閣議決定・③多数決による決定
- アメリカの保守とリベラル
- 上院と下院
- 連邦議会の構成・・・・・・上院と下院
- 「良識の府」「民衆の府」と連邦議会選挙
- 上院の「条約承 認権」と「人事承認権」
- アメリカの選挙権の歴史
- 有権者登録が必要なアメリカの選挙権
- 上院議長は副大統領/議会で多数の議席を占める「多数党」であることが重要
- 院内総務と院内幹事
- 移民または移民2世の連邦議会議員
- 急増する連邦議会女性議員
- 共和党女性候補が抱えるジレンマ
- 連邦議会議員の仕事
- 連邦議会では議員はほとんど議場にいない
- フロアマネジャーと少数の議員だけ
- /議員! 人でも法案を提出できる
- 徹底した委員会中心主義
- 委員会には大きな権限が与えられている
- 補佐官が議会活動を補佐
- 議会補佐官は党派性を持つ
- 【コラム】事務的な補佐の必要 性から始まった補佐官制度
- 【コラム】 議会補佐官の選挙活動/法案の作成と最終チェック
- 法案を審査対象にするかどうかは委員長が決める
- 逐条審査および修正案の検討委員会の報告書
- 下院では全院委員会から本会議へ
- 上院での法案審議
- フィリバスターという上院ルール
- フィリバスターとクローチャー
- フィリバスターは依然として有効
- 【コラム】 フィリバスターと「核オプション」
- 【コラム】『スミス都へ行く』
- 連邦議会では法案は次々 と修正される
- 同じ法案の内容が上院と下院で異なることもある
- 両院協議会で最終的な法 案を作成/法案の可決成立までのプロセス
- 変換型議会での予算審議プロセス
- 劇場型議会ではスキャンダルが追及される
- 連邦議会は「変換型議会」
- 連邦議会議員は忙しい
- 予算編成は連邦議会の重要な仕事
- 「予算教書」と「予算」
- 連邦議会での予算審議
- 予算審議のプロセス
- 「予算決議」と「歳出法」
- 歳入関連法案と大統領の署名
- つなぎ予算をつくって一時しのぎをする
- ガバメント・シャットダウンが起きる
- トランプ大統領とガバメント・シャットダウン
- 中間選挙と民主党共和党
- アメリカ国民の議会支持率は低い
- 党議拘束がかかる日本
- 連邦議会では党議拘束がかからない
- 1票の違いがモノを言う
- バイデン政権でも「5対50」
- 統一政府と分割政府
- 中国関連法案では民主党と共和党が協力
- 大統領は法律案を提出できないのか
- 民主党と共和党の政策的傾向の比較
- 中間選挙の結果を見る
- 予備選挙の日程や実施方法は州によって異なる
- ワイオミング州での予備選挙/州への下院議席配分が変わった
- 「立法府」の「行政府」 に対するチェック・アンド・バランス
- 連邦議会の制度
- 第4章 強大な権限を持つアメリカ大統領
- 大統領の権限
- アメリカ歴代大統領のランキング
- 「トランプ大統領とアメリカ議会』を上梓
- トランプ大統領の4年間
- 第30回大統領選挙ではバイデン大統領が誕生
- 第30回大統領選挙では?
- 行政権を持つ大統領を国民が選ぶ
- 大統領制の特徴・大統領と連邦議会の関係
- 大統領の軍事「戦争権限法」をめぐる矛権限
- 議会による「戦争権限法」
- 議論が続く「戦争権限法」盾と現実
- 条約締結権と任命権・免権
- 議会に対する大統領の権限
- 行政命令権と国家元首としての権限
- 徹底した抑制権の配分
- 大統領になるための資格と任期
- 大統領になるための資格
- 大統領の任期
- 大統領の承継
- 再選回数の規定
- ピラミッド型の行政機構
- アメリカの行政機構
- 大統領府とスタッフ
- 政治任用者とメリット制が混在
- 大統領令
- 大統領の一般教書演説
- 一般教書演説とバイデン大統領の後方に座る2人の女性
- 副大統領はランニングメイト
- 上院議員席にはキャンディ・デスクがある
- 2022年3月の大統領一般教書演説
- 2024年3月の大統領一般教書演説
- 大統領選挙のしくみ
- 大統領選挙の方法
- 2016年と2020年の大統領選挙
- バイデン政権の4年間と2024年大統領選挙・トランプ前大統領の復活
- バイデン大統領の支持率
- バイデン大統領の支持率低下の理由
- アフガン紛争の終結とアメリカ国内の厭戦気分
- バイデン大統領の経済政策
- 民主党の次の大統領候補は?
- カマラ・ ハリス副大統領
- カマラ・ハリス大統領候補
- 共和党の大統領候補/共和党の中の熱狂的なトランプ支持者
- 若者はどう思っているのだろうか
- 2024年大統領選挙・・・・・・トランプ前大統領の復活
- 大統領の権限
- 終章 世界の中の日本の役割を考える
- 試行錯誤する民主主義国家
- バイデン大統領が主導した民主主義サミット
- 民主主義国家の数は減少している
- 日米を中心とした多様な連携
- 日米豪印戦略対話
- インド太平洋経済枠組み
- 地域的な包括的経済連携協定
- 日本の役割
- 日本の地政学的位置
- 日米協力と日本の安全保障
- 日本にとっての日米関係と世界秩序
- 難しいかじ取りを迫られる時代
- 試行錯誤する民主主義国家
- おわりに
書籍紹介
この本は、現代のアメリカ社会や政治、文化の動向を深く掘り下げ、それを日本や世界の視点と結びつけて解説する内容となっています。中林さんは、アメリカの政治や社会問題に精通した研究者であり、長年アメリカの現場に足を運び、現地の声を丁寧に拾い集めてきた経験がこの本に反映されています。彼女の鋭い観察力とわかりやすい筆致が、複雑なテーマを身近に感じさせてくれます。
本書では、アメリカの分断やポピュリズムの台頭、种族やジェンダーにまつわる議論、さらには国際関係におけるアメリカの役割など、幅広いトピックが取り上げられています。特に、2020年代のアメリカが直面している社会の変化や、政治的な対立がどのように形成されてきたのか、その背景を丁寧に紐解いています。たとえば、トランプ政権やバイデン政権下での出来事を通じて、アメリカの民主主義の現状や課題が浮き彫りにされています。これらの話題は、遠い国の話ではなく、日本や世界全体の未来にも深く関わってくるため、読者にとって大きな気づきを与えてくれるでしょう。
アメリカの日常的なエピソードや、そこで暮らす人々の声が織り交ぜられているため、データや理論だけでなく、人間らしい視点でアメリカを理解できます。また、日本との比較を通じて、読者が自分たちの社会を見つめ直すきっかけを提供してくれる点も魅力的です。たとえば、アメリカの教育や医療の課題が紹介される中で、日本の制度や価値観との違いが浮かび上がり、双方の強みや課題を考えるヒントが得られます。
この本は、アメリカに興味がある方はもちろん、グローバルな視点で現代社会を理解したい方にもおすすめです。ニュースやSNSで飛び交う断片的な情報だけでは見えにくい、アメリカの「今」の本質を捉える手助けとなるでしょう。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
ガソリン価格高騰が貧困層を直撃

ウクライナ戦争によるガソリン価格の高騰が原因で、2022年のアメリカのインフレ率が上がっています。戦争が長引くにつれて支援疲れが起きていることは、バイデン大統領の政策支持率が11ポイント下がっていることからわかります。
実際、バイデン大統領が大統領選挙で勝利した2020年11月以降、ガソリン価格は急上昇し、自動車社会であるアメリカでは死活問題になりました。
新しいエネルギー発電が確立されるまでの今後10年間くらいは、石油に頼らざるを得ないのでアラブ諸国から石油輸入を増やそうと、サルマン皇太子と面会しました。これが痛烈な批判を浴び、人権派と共和党支援者から冷ややかな目で見られます。アメリカで石油を増産すればいいという主張がまかり通っていたため、バイデン大統領の支持率は下がる続けることになったのです。
ハリス候補が、トランプ候補に敗北した理由は経済です。第1次トランプ政権の経済政策が良かったと実感した国民が多いです。雇用の増加はかなわなかったものの、大型減税などの過去の政策が支持を得た結果でしょう。