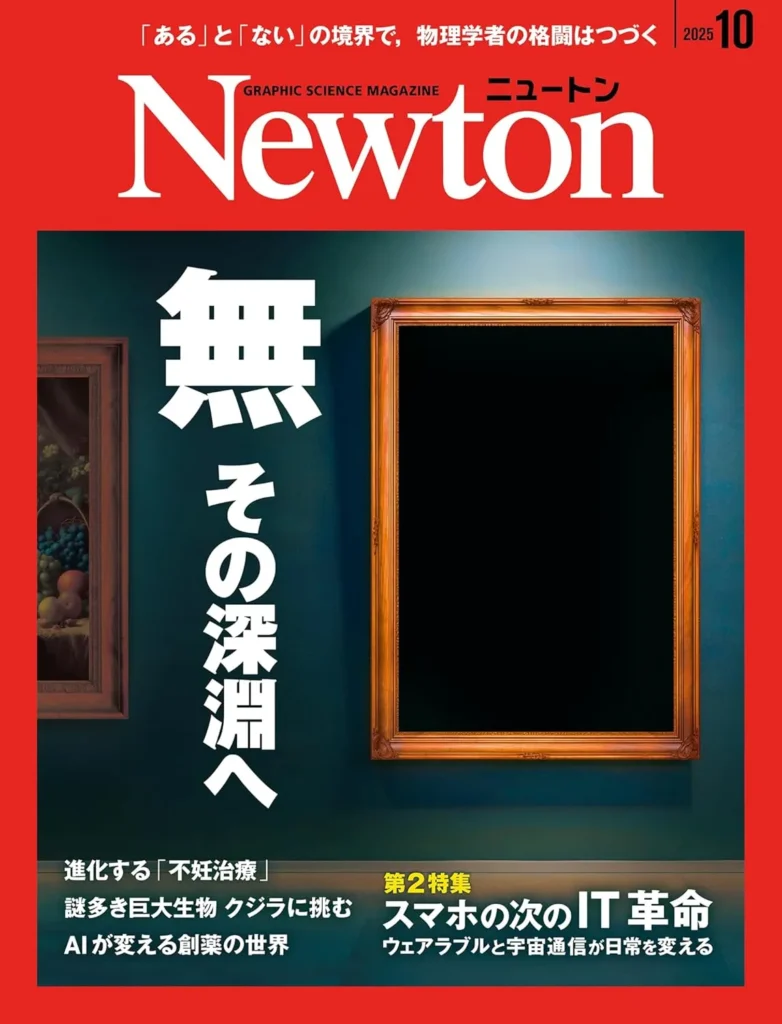
発売日 2025年8月26日
ページ数 144p
ISSN 0286-0651
もくじ
- FOCUS
- 鼻毛に着想を得たエアフィルター
- 反陽子の 量子ビット
- 観測史上最大のブラックホール合体
- 7 古代エジプト人のゲノムが初解析
- ダムの建設で地軸が移動した
- 脳の細胞を置きかえる難病治療
- From 朝日新聞
- カムチャツカ地震, 前回から70年あまりで発生の謎
- スズメなど7種の鳥が「絶滅危惧種」並みに減少
- 拍手の正体、両手がぶつかりあう音じゃなかった
- 暗号が瞬時に解かれる脅威
- 第1特集 Newton Special 「真空」 と向き合いつづけて科学は発展した 無 その深淵へ
- 監修 有賀暢迪
- 執筆 中野太郎/三澤龍志 (編集部)
- 物理学における「無」とは, 物質が何もない 「真空状態」だ。人類と無の格闘の歴史は,科学の発展の歴史でもある。無という概念と向き合ってきた,人類の物語を紹介しよう。
- 連載 中村玄クジラに挑む クジラは多くの謎に包まれた生物
- 聞き手 追野貴大 (編集部)
- クジラは海での生活に完全適応した哺乳類だ。東京海洋大学の中村玄准教授に、体のつくりからクジラの生態を解き明かす研究についてうかがった。
- ユークリッド 宇宙望遠鏡 開眼 宇宙を支配する謎の物質とエネルギーを解明する
- 監修 宮武広直
- 執筆 荒舩良孝
- 宇宙に存在するエネルギーのうち 約95%は謎に包まれている。この謎を解くために打ち上げられた「ユークリッド宇宙望遠鏡」の美しい観測画像を紹介しよう。
- 第2特集 Newton Special スマホの次のIT革命 ウェアラブルと宇宙通信が日常を変える
- 監修 塚本昌彦
- 執筆 尾崎太一
- ITの進化は,暮らしを革新的に変えつつある。AIで劇的な変化をとげるウェアラブルから現実と仮想をつなぐ空間コンピューティングまで, ITの最前線をみていこう。
- Nature View あざむく生物図鑑「擬態」によって生き抜く、生存戰略
- 監修 小宮輝之
- 執筆蓁袋摩耶
- 「擬態」とは見た目などが別の何かに似ることで、生物の認識をまどわせることだ。見た目だけでなく、においや音に似ることもある。生物の個性的な擬態を紹介しよう。
- AI創薬 最新レポート 薬の探索から設計へ Alpha Foldの衝撃
- 監修 森脇由隆
- 執筆 梶原洵子
- 2024年のノーベル化学賞でも話題となったAI 「AlphaFold」は医薬品の開発 (創薬) に革新をもた らした。 AIを利用した 「AI創薬」の最新状況をのぞいてみよう。
- 日本建築 ビジュアルガイド 独自の意匠や技法をみがき,個性的な寺社や城郭がうまれた
- 監修 野村俊一
- 執筆 北原逸美
- 日本では,国内で独自の意匠や技法を洗練させ、さまざまな名建築 を生みだしてきた。飛鳥時代から江戸時代までの, 個性豊かな寺社建築と城郭建築をながめてみよう。
- 進化する「不妊治療」 AI活用・遠隔操作・遺伝子解析 生殖補助医療の最前線
- 監修 久慈直昭
- 執筆 橋本裕子
- 日本では赤ちゃんの10人に一人が「生殖補助医療」という高度な不妊治療によって生まれている。AIや遺伝子解析などを取り入れた不妊治療の最新事情を紹介しよう。
目次
Focus
鼻毛に着想を得たエアフィルター
ジャンル:工学
出典 Bioinspired capillary force-driven super-adhesive filter
Nature, 2025年6月18日
鼻毛には花粉などの異物が体内に入るのを防ぐはたらきがあります。この仕組みをフィルターに応用できると考えた韓国中央大学校の大学院生は、鼻毛の機能を模したエアフィルターの開発に取り組みました。
一般のエアフィルターは、材料となる分子と粒子の間にはたらく分子間力を使って粒子を吸着します。鼻毛は、鼻水に濡れたときに毛細管力で粒子を吸着します。毛細管力による吸着はかなり強力です。
そこで、ポリエステルの繊維にシリコンオイルをスプレーすることで、吸着力を増したエアフィルターを発明しました。室内野球場などの実環境でテストした結果、ちゃんとした性能があることが明らかになっています。フィルターやオイルをかけ直せば、何度でも使える実用性の高いものだと語っているようです。
AI創薬
監修:森脇由隆 東京科学大学難治疾患研究所准教授
執筆者:梶原洵子
従来の創薬は、天然に存在する化合物を改良することで、薬となる化合物の開発が行われてきました。しかし、AIによって天然に存在しない化合物をつくり、新しい薬をつくれるかもしれません。
2024年にノーベル化学賞を受賞したデイビド・ベイカー博士らは、タンパク質をAIで設計する研究を進めています。すでに、ヘビの毒に対する薬をつくるタンパク質の設計に成功しています。
アミノ酸が再結成されるデータをAIに学習させ、新しいタンパク質を自動生成するというものです。技術が進展すれば、標的のタンパク質に結合するタンパク質を設計できるようになり、薬を自在に設計できるようになるかもしれません。
