※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
運動・からだ図解 細胞生物学の基本
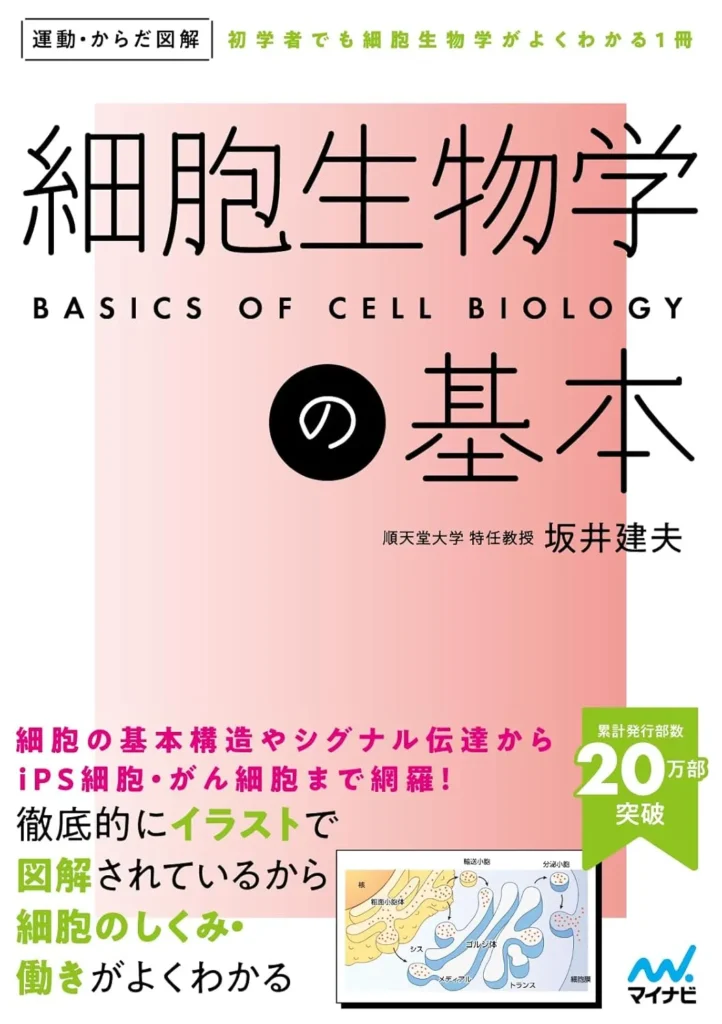
坂井建雄
順天堂大学保健医療学部特任教授。解剖学者。日本医史学会副理事長。医学博士。
マイナビ出版
- はじめに
- 本書の使い方
- 第1章 細胞は生命体の最小単位
- 細胞生物学とはどんな学問?
- 生命が生命である条件
- 生物のつくりは階層構造
- 体内の組織と器官
- 細胞は体の最小単位
- 細胞のサイズはさまざま
- 単細胞生物と多細胞生物
- 細胞の種類
- 細胞の基本構造
- 細胞内の分子の機能
- 糖
- たんぱく質
- 脂質
- ビタミン
- ミネラル
- 代謝でエネルギーを獲得する
- 解糖系とは
- 解糖系のメカニズム
- ミトコンドリアによるエネルギー生産
- 葉緑体と光合成
- 細胞研究の歴史
- 細胞の発見
- 遺伝子研究の進歩
- COLUMN 細胞や生命をつくって理解する合成生物学
- 第2章 細胞の膜と内部構造
- 細胞は膜に包まれている
- リン脂質の働き
- 単位膜の働き
- 細胞小器官
- 細胞を支える細胞骨格
- 細胞内で物質を移動させるには
- 膜たんぱく質の働き
- 膜輸送たんぱく質の役割
- イオンチャネルとは
- 体を満たす液体と浸透圧
- 神経刺激におけるポンプとチャネル
- 輸送体の故障と病気
- 細胞の結合と接着
- 細胞の分解作用
- オートファジー
- エンドサイトーシス
- ノーベル賞とオートファジー研究
- COLUMN たんぱく質の形を予測するAI
- 第3章 細胞内外の情報のやり取り
- 細胞もコミュニケーションを取る
- シグナル伝達とは
- 細胞間シグナル伝達の種類
- 細胞外のシグナル伝達
- 受容体の働き
- 受容体たんぱく質の種類
- 神経伝達物質の役割
- 神経伝達物質とイオンチャネル
- チャネル型受容体とイオンチャネル
- チャネル型受容体とシグナル伝達
- シグナル伝達の流れ
- Gたんぱく質
- Gたんぱく質の活性化
- セカンドメッセンジャー
- 細胞内のリン酸化・シグナル伝達
- 細胞内シグナル伝達を担う分子
- 細胞が死ぬときの情報伝達
- 情報伝達の異常と病気の発生
- 服薬と情報伝達
- COLUMN 注目のシグナル伝達方式「エクソソーム」
- 第4章 遺伝情報を運ぶDNA
- 遺伝子の保管場所
- 遺伝子の役割
- デオキシリボ核酸とリボ核酸
- DNAとRNAの違い
- シャルガフの法則とは
- DNAの二重らせん構造
- DNAの複製が進む方向
- RNAを構成する4種類の塩基
- さまざまなRNA
- メッセンジャーRNA
- トランスファーRNA
- リボソームRNA
- RNAとコドン
- 遺伝子とゲノム
- DNAの配列決定
- RNAの配列決定
- ヒトゲノム配列の解析
- DNAを分析するには
- メンデルの3つの法則
- メンデルの法則に従わない遺伝
- 遺伝のしくみ
- 相同組換え
- 減数分裂
- 生殖細胞
- 身体は腸からできあがる
- 発生のしくみ
- 原口背唇部と形成体
- 眼杯と誘導
- COLUMN 遺伝子の数が多いほど高等生物なのか?
- 第5章 幹細胞とiPS細胞
- 姿形を変えられる細胞
- 細胞を補充する幹細胞
- 幹細胞の2つの機能
- 組織幹細胞と多能性幹細胞
- 体性幹細胞と胚性幹細胞
- 幹細胞の分化誘導のしくみ
- 遺伝子組換え作物とは
- 再生医療とは
- 多能性幹細胞を活用した再生医療
- あらゆる細胞に分化できる細胞
- ES細胞
- iPS細胞
- ES細胞の課題とiPS細胞の発見
- 幹細胞とクローン技術の歴史
- iPS細胞に期待される役割
- 再生医療の課題
- COLUMN 研究不正STAP細胞だけではない
- 第6章 がん細胞
- 遺伝子の変異
- がんの正体とは
- がん組織の特性
- がんのステージ
- がんの原因
- がん原遺伝子とがん抑制遺伝子
- がんは遺伝性の病気?
- がん治療の主な種類
- がん治療の歴史
- 最近のがん治療
- 分子標的薬
- CAR-T療法
- ウイルス療法
書籍紹介
初学者から専門家までを対象に、細胞の世界を徹底してイラストで解説する画期的な書籍です。細胞の基本的な構造からその機能、さらにはiPS細胞やがん細胞に至るまでの広範なトピックをカバーしています。
- 視覚的学習の推進: 生物学の複雑な概念を理解するためには、視覚的な手助けが非常に重要です。この書籍はその点に特化しており、細胞の膜、内部構造、遺伝情報の運び方など、すべてがわかりやすいイラストで説明されています。
- 細胞の基本から専門的な話題まで: 生命体の最小単位である細胞から、現代生物学の最前線である幹細胞やiPS細胞、そしてがん細胞まで幅広く網羅。この一冊で細胞生物学の全貌が理解できる構成になっています。
- 学習者に優しい設計: 初学者にとっては、細胞の基本的な構造や働きが理解できることで、より深い学習への扉が開かれます。一方、専門家や学生にとっては、視覚的な理解が実験や研究に直接活かせるため、非常に有益です。
- 監修者による信頼性: 坂井建雄氏は順天堂大学保健医療学部特任教授であり、そのキャリアは東京大学からドイツ留学、そして現在のポジションまで多岐にわたります。彼の経験と知識が、この書籍の内容の深さと正確さを保証しています。
一般的に細胞生物学の学習者や教育者から期待されているのは、視覚的な理解を深める手助けになることです。特に、学生や研究者がこの書籍を活用すれば、細胞の動きや構造をより直感的に理解することが可能になるでしょう。
細胞の世界を視覚的に学びたい方々にとって、まさに必携の一冊です。坂井建雄氏の豊富な経験と、視覚的学習へのアプローチが融合したこの書籍は、細胞生物学の理解を飛躍的に向上させること間違いなしです。生物学のファン、新規学習者、教育者にとって、見逃せない内容となっています。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
細胞もコミュニケーションを取る

多細胞生物は数多くの細胞が集まってできています。個々の細胞が好き勝手に振る舞っていては、一つの生物として存在することはできません。細胞同士が環境に応じてお互いに情報を伝えて、指示を出したり命令に従ったりします。
指示の内容は、タンパク質をつくる指示もあれば、積極的に細胞分裂を行って増殖するといったものもあります。不要だからという理由で死ぬように誘導することもあります。受精卵から体がつくられる過程では、別の細胞に変わる分化という現象が起きます。この分化もコミュニケーションであり、連続的に受精卵の成長と細胞の分化が行われるのです。
ヒトゲノム配列の解析

1900年にアメリカのエネルギー省と厚生省によって、ヒトゲノム計画が立ち上げられました。この計画は、30億塩基対にもなるヒトのゲノムの全塩基配列を解読することを目指していました。当時のサンガー法では、一度に数百塩基しか調べられませんでした。
ヒトゲノムを10万~20万塩基対の断片に分け、それぞれを大腸菌に挿入します。大腸菌が分裂・増殖するごとにヒトゲノムの断片も複製されます。これらの断片を大腸菌から取り出し、さらに複製し、再びランダムに断片化します。この断片をサンガー法で読み取り、重複する配列を手掛かりに元の配列に組み立てていきます。この方法により、2003年にはヒトゲノムのほぼ全ての塩基配列が明らかになりました。
2006年には、次世代シーケンサーという革新的なDNA解析装置が登場しました。現在では、この技術を使って、約2日間で約128人分のゲノムを、一人あたり約10万円で解析することが可能です。
がん組織の特性

悪性腫瘍であるがんは無秩序に細胞増殖できる性質があります。低酸素状態になると、HIF-1αという転写因子が安定化し、VEGFを生産します。このVEGFが血管内の受容体に結合すると、血管新生を促進し、がん細胞は必要な栄養や酸素を受け取ることができます。
栄養や酸素を確保したがん組織は大きくなり、進行がんとなります。発達したがんは上皮細胞との接着性が弱くなり、結合組織内に進入します。これを浸潤と呼びます。やがて血管に侵入すると、血小板をまとって免疫細胞からの攻撃を回避し、別の場所で血管外に出て増殖します。これが転移と呼ばれています。

