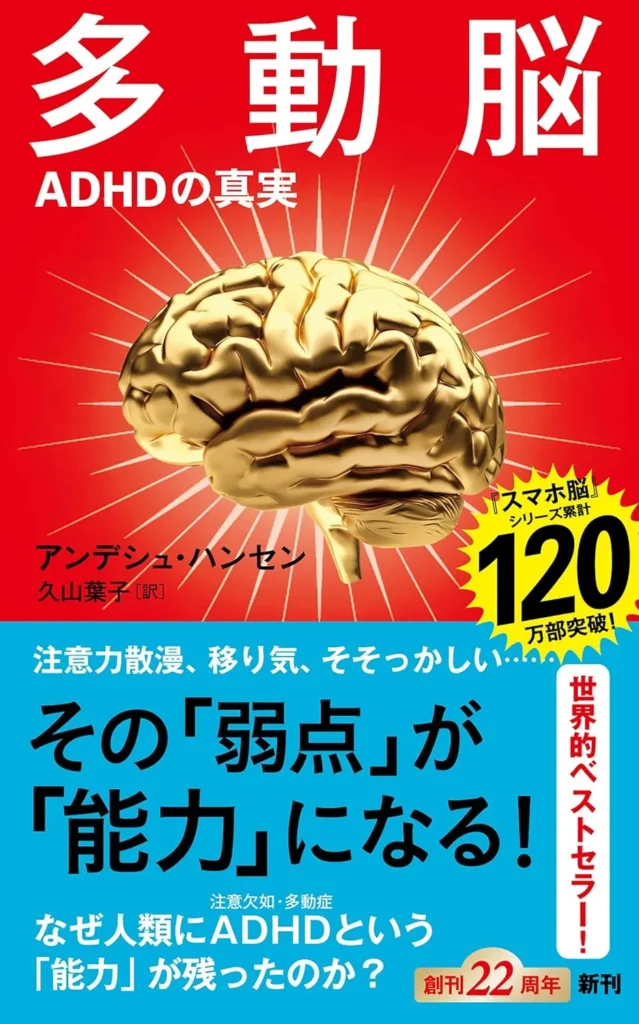※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
多動脳
ADHDの真実
アンデシュ・ハンセン
精神科医。世界的ベストセラー作家。
新潮社
- 日本の読者の皆さんへ
- まえがき ADHDには〈強み〉がある
- 第1章 ADHDって何?
- ADHDは広いグレーゾーン
- 診断名と理解の変遷
- 人間の本質は複雑なもの
- 診断は1つなのに複数の要因
- コラム
- ADHDは成長すると消える?
- 男子に多い?
- ADHDとADD
- 第2章 この世界は退屈すぎる!
- 集中できないのはわけがある
- 少し違ったドーパミン受容体
- しつけや食 生活のせい?
- ADHDと遺伝子
- 依存症とADHD
- 世界が面白くない
- SNSがドラッグになるわけ
- ドーパミンの真の役割
- 脳が乗っ取られる!
- 自己治療の表と裏
- コラム ADHDの他の要因
- 第3章 人類の放浪と〈ADHD遺伝子〉
- 人類の長い放浪
- 「探検家遺伝子」の分布の違い
- 〈ADHD遺伝子〉と農耕の始まり
- 農耕民vs狩猟民
- 主張と証明の線引き
- 生き延びたから子孫がいる
- 失敗と進化
- 突然変異から生まれた性格
- 人類みなADHD?
- 第4章 遺伝子と好奇心
- 政治と白鳥と遺伝子
- 新奇探索傾向
- 群れの中で際立つ特質
- 第5章 ぼんやり脳はクリエイティブ
- ブレインストーミングの能力
- 〈ぼんやり脳〉には意味がある
- すぐ気が散る人はクリエイティブ?
- 意識の門番「視床」
- 「創造性」とは「正しい方向に向かった衝動」
- グループ内でのADHDの役割/ADHDと創造性
- 集中を「オフにする」
- アイデアを思いつきやすい脳
- まとめ
- コラム 薬で創造性が下がる?
- 第6章 ハイパーフォーカス脳
- 集中力マックスorゼロ
- ADHDに向く仕事
- 常にごほうびが必要がない
- まとめ
- 第7章 起業家脳
- 起業家の遺伝子
- 刺激的な仕事に燃える性質
- スーパー起業家
- まとめ
- 第8章 運動は天然の治療薬
- ゲームがうまくなるには
- 薬か運動か
- 〈弱み〉を治し、〈強み〉を維持章するには
- ドーパミン工場を脳内に作る
- 前頭葉強化法
- 運動vsADHD治療薬50種類
- ドーパミンを上げる運動以外の方法
- 究極のライフハック
- まとめ
- コラム 運動で心配や不安を吹き飛ばす
- 第9章 人間は学校に不向き?
- フリークライミングとノーベル賞
- ADHDに「完璧な」学校?
- 運動を 増やし、スマホを減らす
- まとめ
- コラム
- 問題児を大人しくさせた薬
- ADHDの薬の仕組み
- 第10章 ADHDが増加するわけ
- 「正常」とADHDのスペクトラム
- 増えるADHD
- 全員に薬を出す?
- ADHD薬の奇跡
- 人は本当に白紙で生まれてくる?
- 遺伝子と性格
- 医師が間違うことはないのか
- 神経多様性と「病気」
- 変わるべき社会
- ADHDの〈強み〉
- あとがき
- 用語集
- 参考文献
- 謝辞
- 訳者あとがき
書籍紹介
本書では、ADHDの特性が注意力散漫や衝動性といった「弱点」と見られがちな側面だけでなく、クリエイティブさや探究心、ハイパーフォーカスといった驚くべき能力にもつながることを強調しています。ハンセンは、ADHD傾向が誰にでもある程度存在するとし、なぜこのような脳の特性が人類の進化の過程で必要だったのかを紐解きます。たとえば、狩猟採集時代には、素早く環境の変化に反応し、リスクを冒して新しい可能性を探る能力が生存に有利だったかもしれないと述べています。こうした視点は、ADHDを現代社会の枠組みだけで判断することの限界を気づかせてくれます。
日本では学童期の子どもの3~7%、成人では2.5%がADHDの診断基準に該当するとされ、スウェーデンやアメリカではさらに高い割合が報告されています。ハンセンは、食生活や現代の生活環境がこの増加に影響している可能性を指摘しつつ、ADHDの特性が現代社会でどう適応できるかを考えさせます。精神科医としての豊富な経験とデータを基に、専門的な内容を平易な言葉で伝えるハンセンの筆致は、読者に安心感を与えます。
ハンセン自身がADHD的な傾向を自認しており、自身の経験を交えた語り口が本書の親しみやすさを増しています。彼は、ADHDの特性を否定的に捉えるのではなく、日常生活の中で肯定的に分析する姿勢を示しており、読者にもそのような視点を持つことを勧めています。この点は、ADHDを持つ人やその周囲の人々にとって、自己理解や他者理解を深めるきっかけとなるでしょう。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
ADHDが増加するわけ
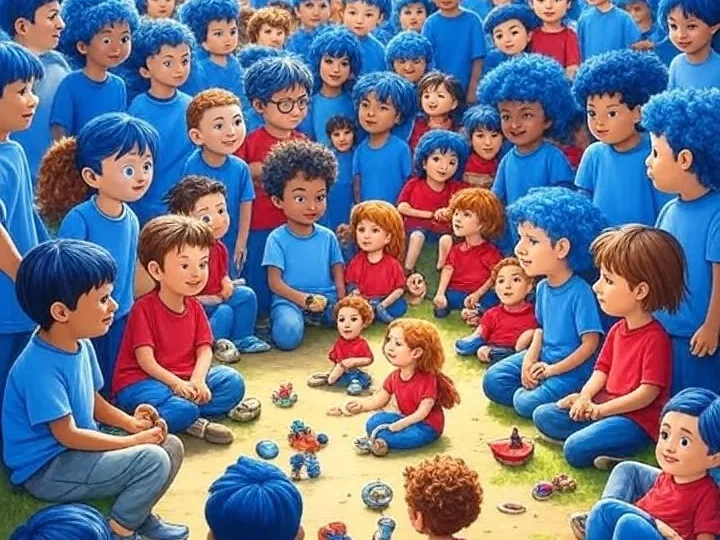
2020までの15年でADHDの人口パーセンテージが4倍~9倍になっています。この爆発的増加は商売が関わっていることが疑わしいです。
今の時代、少しでも精神的に問題があれば診断を受け、薬によって治療するというのが当たり前です。しかし、たいていの場合は性急に診断が下され、好奇心やエネルギーの強さが発達障害と取り違えられてしまっています。
その取り違えられている可能性は数字現れています。同じ学年でも遅い時期に生まれた子供に発達障害が多いです。その差は40%もの開きがあります。12月と1月で誕生時の環境が大きく異なるわけではありません。年が明けたからといって急にADHDの子どもが生まれる可能性が下がるわけでもありません。ただ、成長の未熟さがADHDだと誤解されるせいです。