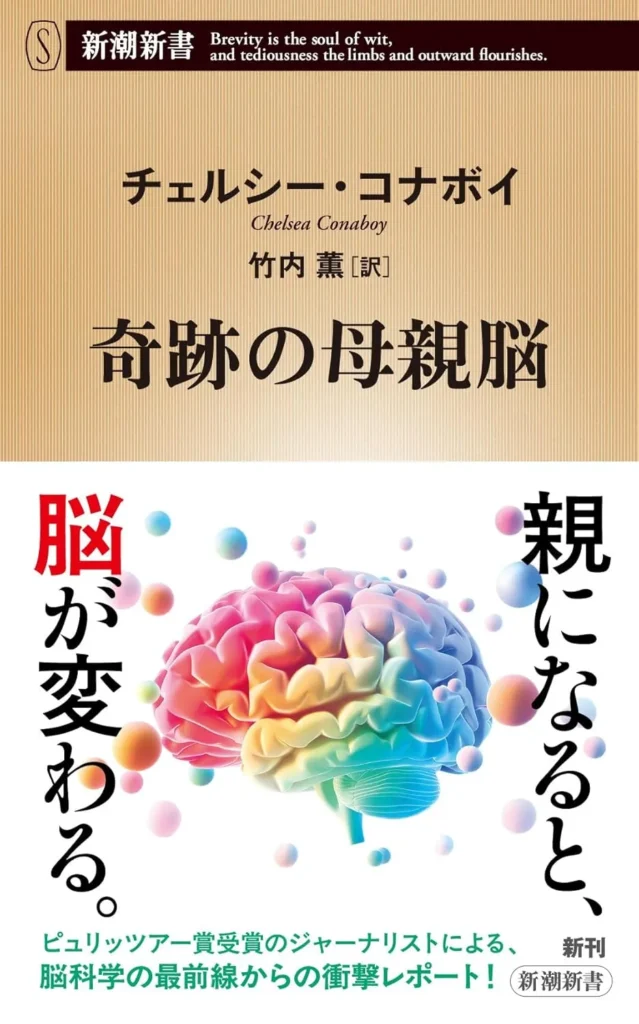※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
奇跡の母親脳
チェルシー・コナボイ
ジャーナリスト。公衆衛生及び健康科学が専門。
新潮社
- 日本の読者のみなさんへ
- まえがき
- 第1章 なぜ母親は自分を「ダメ」だと思うのか?
- 動かなくなった赤ちゃん
- ダメな母親
- 母親の苦悩は正常か
- 出産は脳を変える
- 科学と母性本能の呪縛
- 母性行動は女性の特性か
- 「母性学研究 の父」
- 重要なのは子育ての「経験値」
- 妊娠は重要な「発達段階」の幕開け
- 第2章 なぜ子供に愛情が湧かないのか?
- 生涯にわたって変化する脳
- 脳とホルモン
- 「親の脳」に何が起こっているか
- 研究者がやっていること
- 愛だけでは十分ではない
- 子育ての原動カ〝かわいらしさ”の持つ力
- 報酬系ネットワーク
- 顕著性ネットワーク
- ホルモンと子育ての関係
- 母性の「動機づけ」の不思議
- なぜ心配に取り憑かれる?
- 極端な没頭と不安
- 赤ちゃんの世話が不安を減らす
- 子育ては快適に変化していく
- 親になることは人生が変化すること
- 第3章 どうしたら子供との絆ができるのか?
- 母子特有の絆?
- 新米親子の絆の築き方
- 早産児の親の脳
- ホメオスタシスとアロスタシス
- 脳内の「買い物リスト」
- 子供によって変容する親の「自己」
- 親の体内に残る胎児細胞
- 母子の絆とドーパミン
- オキシトシン の意外な役割
- 自閉症児の親やうつ病の親の脳は?
- 子供の発達は母親の責任か
- 母親業と科学的母性の台頭
- 現代の母親の呪縛
- 脳の可塑性こそが鍵
- 子育ては母親だけのものか
- 母親の脳の変化の発見
- 脳の変化には悪影響がある?
- 父親の育児はどうか
- 父親の脳の変化
- 父親に関する研究の少なさ
- 経験が脳を作る
- マスコットを心に置く
- 第4章 どうしたらうつと不安から逃れられる?
- 「自分の赤ちゃんではないような感じ」
- 産後うつとは何か
- うつ病のリスク
- 産後うつの多様さ
- 産後うつの脳の特徴
- 「ストレスホルモン」は少ない方が良い?
- コルチゾールの役割
- 育児の舞台裏で働くスタッフ
- メンタライゼーション
- 「あなたは私がなりたいすべてなの」
- 育児する脳の生理的基盤の重要性
- 依存症と親の脳
- 遺伝子とうつのリスク
- 心音のない赤ちゃん
- 研究結果と「膨大なノイズ」
- 「逆境体験」の影響
- 初の産後うつ治療薬ズルレッソ
- SSRIとはどんな薬か
- 産後うつは「悲しみの表現」?
- 「自然な」分娩の「大きな嘘」
- 出産のPTSD
- PTSDと心理的成長
- 異例の出産経験
- 第5章 自分を取り戻し、さらに成長するには
- 「マミーブレイン」現象
- 妊娠中と産後の認知機能低下
- 記憶障害はなぜ起こるか
- 睡眠が認知能力に及ぼす影響
- 睡眠介入の必要性
- 親になると強化される能力
- 親の脳内の「新たな内部モデル」
- 子育てがもたらすもの
- 「畏敬の念」が認識を変える
- 第6章 「親の脳の科学」が未来を変える
- “正しい選択”
- 母親は科学を知るべきか?
- 謎ばかりの親の脳の科学
- 胎児細胞の謎
- なぜ妊婦が科学研究で軽視されるのか
- 残された問題
- 愛着理論は「金字塔」か
- さらなる科学的証拠は必要?
- 科学と哲学のギャップ
- 「より広範な意識の変革」へ
- 無力感に置き換わるもの
- 訳者
- あとがき 母性神話よ、さようなら
書籍紹介
この本は、妊娠や出産、育児がもたらす脳の「再編」に焦点を当て、母親だけでなく父親や養子縁組で子育てをする人々の脳にも影響を与えるプロセスを明らかにします。ピュリッツアー賞を受賞したジャーナリストである著者が、科学的な研究を丁寧に取材し、一般の読者にもわかりやすくまとめ上げた本書は、子育てにまつわる多くの疑問や悩みに新たな光を投じます。
妊娠や出産によって女性の脳は劇的に変化し、イライラや物忘れ、気分の落ち込みといった一時的な困難が起こりやすい一方で、驚くべき能力が育まれると著者は説明します。例えば、赤ちゃんのわずかな表情や仕草を読み取る鋭い感受性や、子育てを通じて高まる共感力。これらは「母性」という言葉だけでは説明しきれない、脳の可塑性による進化の産物だとされています。さらに興味深いのは、こうした変化が父親や非生物学的親にも見られる点です。育児に積極的に関わることで、男性の脳もまた神経科学的な変化を遂げ、子どもとの絆を深めるための新たな回路が形成されるのです。
チェルシー・コナボイは、自身の二人の息子の母としての経験も交えながら、科学的データと個人的な視点を織り交ぜて語ります。彼女は、従来の「母性神話」—母親は生まれつき子育てに適しているという固定観念—に疑問を投げかけ、子育ては経験と脳の適応によって築かれるものだと強調します。この視点は、子育てに悩む多くの親にとって、大きな安心感を与えるでしょう。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
研究者がやっていること

デュラックの研究室が行ったのは齧歯類の行動と生理機能を正確に捜査して、脳を顕微鏡で観察するといったものです。脳の領域を制限して、母性行動のどの部分が失われるかといった研究をする。妊娠中の齧歯類にストレスを与えたり、子と引き離したりして、長期的な影響を研究するといったものもあります。研究対象の脳組織は分析用に薄切りにして冷凍保存されます。
人間で同じように研究することはできないでしょう。人間で行うのは、指定された課題への取り組み、妊娠期間中の血中ホルモン濃度の調査、子育てに似た行動時の脳の反応などの研究です。実際の子育ての複雑さや人生における様々な変化を考慮しながら慎重に研究結果を解釈しています。
研究グループはさまざまな測定結果から、人間の親の物語の1コマの立ち位置を解明しようとしています。各動物実験の知見を参考に、進化の過程を経ても、様々な動物の親の脳が似たような反応をすることが確認されています。研究者たちは、子育ての脚本構成を解き明かそうとしているのです。